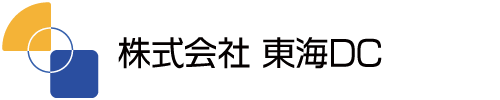狭い道で注意して走っていたつもりでも、すれ違い中にぶつかってしまうと責任が問われます。
原則、過失割合は5:5になるのですが、どこまで寄っていたか、止まっていたかなど、細かな状況が大きく響いてくるものです。
この記事では、狭い道でのすれ違い事故における基本的な過失割合から状況別の判断、さらに具体的なケースまで紹介します。
すれ違い事故の過失割合
狭い道でのすれ違い中に起こる事故、一見どちらが悪いとも言えないケースが多いですよね。
ここでは、そんなすれ違い事故の過失割合について、基本的な考え方を解説していきます。
基本的には5:5

狭い道ですれ違うときは、互いに減速し、ぶつからないように気をつけながら進むのが前提です。
だからこそ、ぶつかってしまった場合には「どちらか一方が完全に悪い」とはされにくく、基本的に5:5の過失割合が適用されます。
しかし、状況によって過失割合は変動するため、注意が必要です。
停止していた場合
もし自分の車が止まっていて、そこに相手がぶつかってきたとしたら…「完全に相手が悪いでしょ!」と思いますよね。
実際、車がきちんと停止していたと認められれば、相手が100%悪いという判断になります。
ただし注意が必要なのが「直前停止」という考え方です。
これは、事故の直前に一瞬止まったような場合、停止とはみなされず、逆に自分にも過失があるとされてしまうケースです。目安としては「3秒以上止まっていたかどうか」。
事故のときに「ちゃんと止まってた」かどうかは自分では判断しにくいので、ぜひドライブレコーダーの映像を確認してみてください。
路肩に寄っていた場合
すれ違いのときに、「こっちは路肩に寄ったのに、あっちが真ん中を突っ込んできた!」というケースもあるでしょう。こんなとき、避けた側の努力はちゃんと評価されます。
具体的には、寄っていた側の過失は30%、相手側が70%と判断されることが多いですが、状況によっては40:60になることもあります。
ハンドル操作のミスがあった場合

うっかりハンドルを切りすぎて事故につながった場合、「著しい過失」と判断されることがあります。
ただし、狭い道では微妙なハンドル操作が求められるので、「少しズレただけ」くらいではそこまで重く見られないことも。そのため、すれ違い事故では10%ほど過失が加算されるケースが一般的です。
すれ違い事故の判例

すれ違い事故は、ぶつかった箇所や車の動き方で過失割合が変わるため、もめごとになりやすいのが特徴です。
しかも、当事者同士の言い分が食い違いやすく、「自分は止まっていた」「相手がはみ出してきた」など、主張がぶつかることも珍しくありません。
こうなると、ドラレコの映像や証言がカギになりますが、場合によっては示談に至らず、裁判にまで発展するケースも…。
ここでは、具体的なケースを紹介しますので、どんなポイントが判断材料になったのかを確認してみてください。
停止していたがドアミラーが接触したケース
車が路肩にしっかり寄せて停止していたところ、通過しようとした車がドアミラー同士を接触させてしまいました。
裁判所の判断はというと、「停止していた側に過失はない」でした。
なぜかというと、通過する車には、ぶつからないように十分な間隔をとる義務があるからです。
ただし、「本当に停止していたか」「どこまで寄せていたか」など、細かい状況が判断材料になります。
見通しの悪いカーブで衝突されたケース
センターラインのないカーブで車同士が正面衝突。
道路は幅が狭く、高低差もあり、見通しも悪い。カーブミラーはあったものの、互いの発見が遅れたことが原因でした。
裁判所は、相手の前方不注意が主な原因としつつも、「カーブミラーで相手の存在を確認できたはず」という理由で、被害者側にも10%の過失を認めました。
狭い交差点で衝突されたケース
車を左に寄せて停止しようとしたところ、相手の車が交差点を左折してきて、道路の中央よりはみ出した状態で衝突。
被害者側は「自分はきちんと左に寄って止まっていたし、これは完全に相手のミス」と主張しました。
そして、ドライブレコーダーの映像解析によって、相手の車が中央線を超えていたことが判明します。結果、0:100という判決になりました。
まとめ
すれ違い事故の基本的な過失割合は5:5ですが、「どこまで寄っていたか」「完全に停止していたか」といった細かい状況で大きく結果が変わります。
「自分には過失がない」と思っても、それを証明できなければ納得いかない過失割合を受け入れざるを得ないことも…。
車にドラレコを設置しているなら、迷わず映像を活用しましょう。もしも映像がはっきりしていなくても。諦める必要はありません。
東海DCでは、専用ソフトウェアを使ってドライブレコーダーのデータを分析し、損傷写真や車両の位置関係、現場の構造をもとに、事故の真実を丁寧に可視化します。
「どう説明すればいいかわからない」「相手に言いくるめられそう」と不安な方は、弁護士を通じてご相談ください。